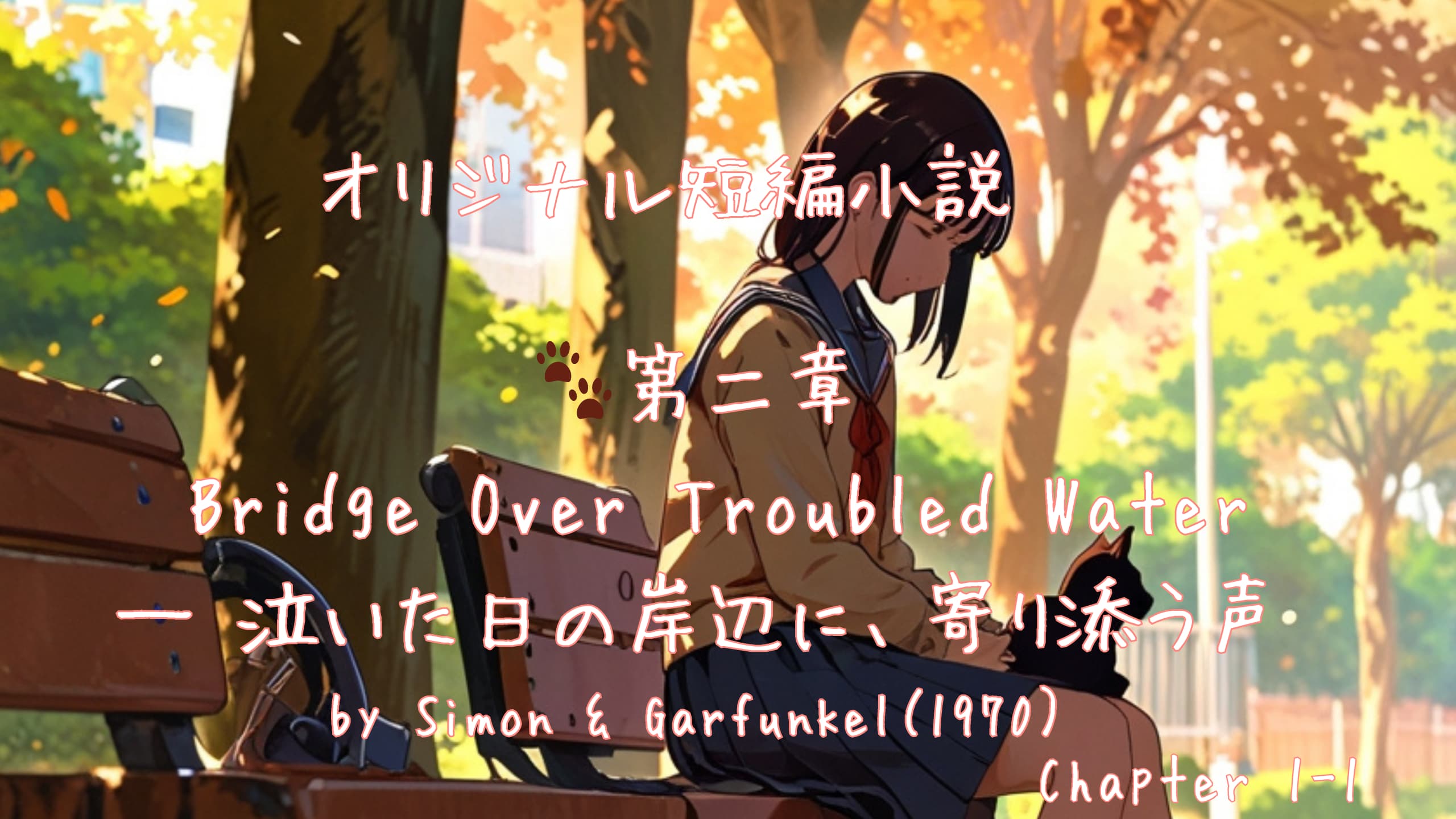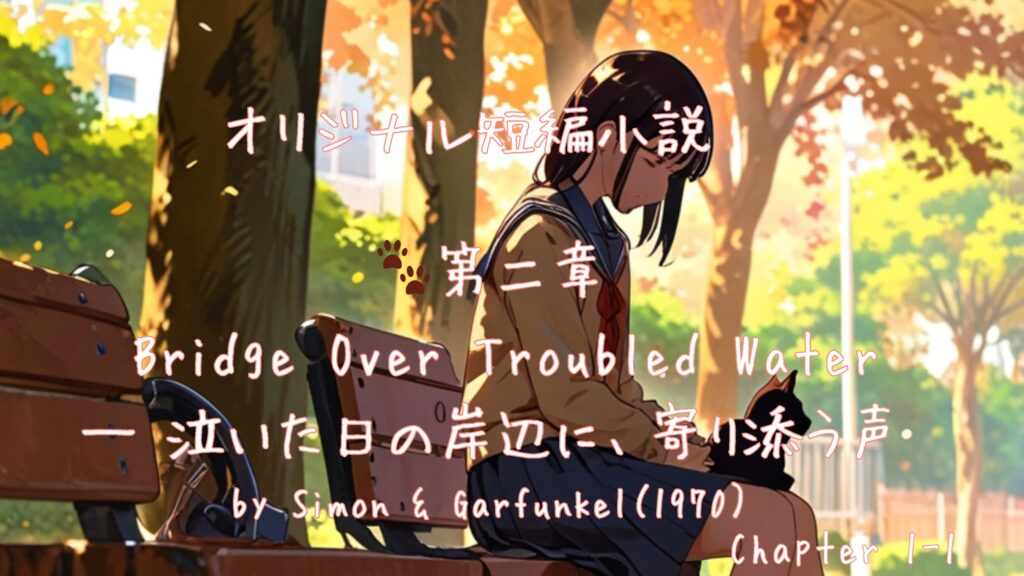
「……ねえ、ルナ。あの日、わたしが泣いてたの、覚えてる?」
ミオはふと、カーテン越しに空を見ながらつぶやく。
『ええ。放課後の校庭の隅。あなたの泣き声、空よりも静かだった』
それは、高校二年の秋。
仲の良かった友人と気まずくなり、教室で笑うことができなくなった日々。
心の中で何度も「ごめん」と「どうして」が交錯していた。
夕暮れの校庭。隅のベンチに一人、膝を抱えて座りこんでいたミオに、ふいに声がかかった。
──『どうして、そんなに涙のにおいがするの?』
見上げた先にいたのは、一匹の黒猫だった。
誰にも話せなかった想いを、彼女はその猫にだけこぼした。
言葉にすることで、涙が止まらなくなった。
それでも、その猫──ルナの声は、ふしぎと心にすっと届いた。
『泣いた分だけ、優しくなれるわ。だから、あなたは間違ってない』
ルナの言葉に、ミオは初めて「自分の気持ちがここにある」と実感した。
その瞬間、誰かの気持ちにふれること、寄り添うことの大切さを心で知ったのだった。
あの時、誰かが言葉をくれたら──
そんなふうに感じた経験が、今の彼女の原点になっている。
人の言葉に耳を傾け、その人の感情の奥にある“ほんとう”を知りたい。
だからこそ、取材という名の対話を通じて、人の気持ちを丁寧にすくい上げたい。
表面的なトレンドではなく、その奥にある“想い”を書きたい。
大学に進学する時、実家を出る時、社会に出たばかりの不安な日々も──
ルナは、いつもそばにいてくれた。
今でも、ミオはそのときの言葉を時折日記に記している。
“大丈夫。間違えたって、歩いた道はきっと意味になる。”
ショート動画風の名言を、ミオは「ルナの声」として記録している。
それは、自分自身の癒しであり、いつか誰かに届く言葉になると信じているから。